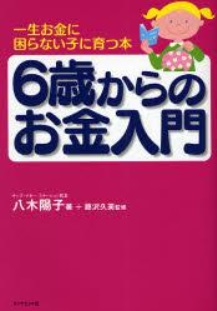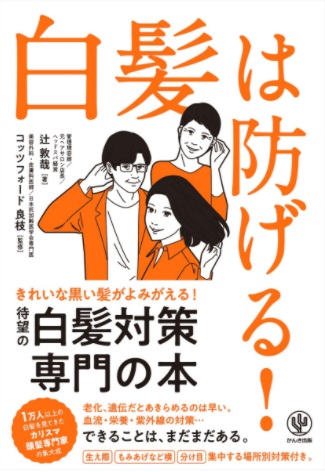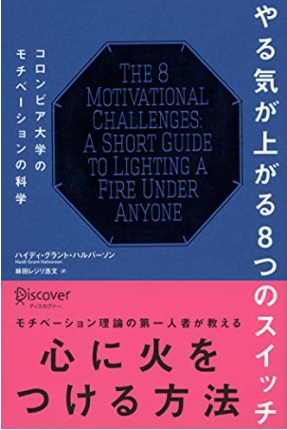キッズ・マネー・ステーション代表の八木陽子さんの著書「6歳からのお金入門」を読みました。
「6歳からのお金入門」とは
おこづかいのあげ方、暮らしの中で学べるお金や経済の仕組み、お金の貯め方・増やし方、お金を借りる、お金を稼ぐなど多くのことを学ぶことができます。
「6歳からのお金入門」というタイトルではありますが、2歳から小学生のお子さんを持つ親まで参考になる内容です。
筆者が伝えたいメッセージ
小さいころから、親がきちんと「お金のしつけ」をすることで、お金(欲望)のコントロールをする力を養い、お金を大切にする、感謝をする気持ちが芽生えさせることができます。それは将来、必ず役に立つはずです。
「6歳からのお金入門」から学んだおこづかいのあげ方
おこづかいのあげ方2大パターン、「報酬制」と「定額制」
報酬制
定義
お手伝いなど働いた分に応じて、おこづかいを渡すもの
メリット
お手伝いを継続しやすく、励みになる。
お金を稼ぐ大変さを実感でき、「お金は労働の対価」という概念が学びやすい。
デメリット
なんでもお金に置き換えたり、お小遣いがもらえないお手伝いをやりたがらないことがある。
定額制
定義
毎月(毎週・毎日)、定められた金額をおこづかいとして渡すもの。
メリット
お手伝いと切り離しているため、お手伝いは家族の一員として当然であることが理解しやすい。
毎回決まった金額なので、「お金のマネジメント」を上達しやすい。
デメリット
忙しくなると、お手伝いをしなくなる。それでも、お小遣いはもらえると思ってしまう。
報酬制と定額制はそれぞれメリットデメリットがあるので、子どもの性格を見ながら、ご両親で方針をきめるといい。
また、筆者は2つをミックスした方法もおすすめしています。
子供に必要なギリギリの金額を定額制にしておき、残りは子どものお手伝い次第というやり方。
「ニーズ」&「ウォンツ」を区別して使い道を決める
ニーズは必要なもの。ウォンツは欲しいもの。おこづかいいでは、まず、ニーズを最優先する習慣をつけよう。
ウォンツの中から何を購入するか工夫したり、試行錯誤することによって、上手にお金を使う練習ができる。
おかねのレッスン方法
◆Step1 今月に買いたいもののリストを書く
消しゴム、キティの下敷き、遠足用のおやつ、おもちゃ付きのお菓子、カードのゲーム、案が、おばあちゃんの誕生日プレゼント
◆Step2 それはニーズなの?ウォンツなの?
- 「必要」なものか、「欲しい」ものか考える
- 必要でないのに、必要だと思い込んでいないか
- ないと困る、学校で使うものか
↓
ニーズの場合、購入する。ウォンツの場合、Step3へ。
◆Step3 それはどうして欲しいの?
- みんなが持っているから
- テレビや雑誌を見て欲しくなった
- お店で見つけて欲しくなった
- あった方がうれしい、便利
- 将来のためになる など…
◆Step4 それを買う前に確認してみよう
- 似たようなものを持っていないか
- すぐに違うものが欲しくならないか
- 誰かから借りることができるものではないか
- 自分で代わりのものを作れないか
- 購入したい順に優先順位をつけ、優先順位が低いものは削る
◆Step5 それを手に入れる方法はどうする?
- 毎月のおこづかい内で手に入る
- 毎月のおこづかいを貯めてから買う
- リサイクルショップなど安いものを探してみる
- 両親に一部負担してもらう
- 誕生日かクリスマス、お年玉まで我慢する
↓
ついに手に入れる!
おこづかい5年間計画ステップアップ術
子供に任せるお金の範囲を、5年間で少しずつステップアップできるような計画を練ろう。
1年目
やること
おこづかい制になれる。
1週間や1カ月ごとのおこづかいで、欲しいお菓子やおもちゃを購入
目的
欲望のコントロールを知る。
買い物のやりとりができるようにする。
2年目
やること
「自分の楽しみのお金」のやりくり
目的
自分が食べるお菓子はおこづかいから支払う。
クリスマスやお誕生日プレゼント以外、おもちゃは自分で買うなど。
3年目
やること
「自分の楽しみのお金」+文房具
目的
学校の文房具を含めたおこづかいにし、世の中には必要な一定経費があることを知る。
4年目
やること
「自分の楽しみのお金」+文房具+習い事のお金
目的
自分の生活ににかかるお金を幅広く知る
5年目
やること
「自分の楽しみのお金」+文房具+習い事のお金+学校関係費
目的
自分名義の口座を作り、学校関係費の引き落としに使う。
銀行・郵便局の口座の使い方を知る。
「6歳からのお金入門」を読んで
おこづかいをあげ始めて1年になりますが、やはりわが家は定額制がいいと再確認できました。
ニーズとウォンツという考え方も、小学生になったら文房具から取り入れたいと思いました。
日ごろからお金や経済の仕組みに関する話もし、もう少し大きくなったら投資などにも挑戦させたいと思います。